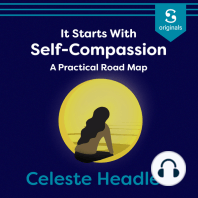Professional Documents
Culture Documents
Wafuugetsumei Poster
Wafuugetsumei Poster
Uploaded by
Eduardo DeerOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Wafuugetsumei Poster
Wafuugetsumei Poster
Uploaded by
Eduardo DeerCopyright:
Available Formats
わ ふう げつ めい にっぽん めい じ ねん つき たいよう うご もと たいいんたいようれき
和 風月名 日本では, 明治5年まで月と太陽の動きを元にした太陰太陽暦
きゅうれき つか つき よ な き せつ ぎょう じ
きゅう れ き つき な ま え
というこよみ
(旧暦)
が使われていて , 月の呼び名も季節や行事
旧暦の月の名前 にあった和風の呼び方がありました。
わ ふう よ かた
きゅうれき つき な まえ ふる つた ゆ らい い み さまざま せつ ただ ふ めい
旧暦の月の名前は , たいへん古くから伝わるものなので , 由来や意味には様々な説があり , どれが正しいのかは不明です。ここでは ,
おも せつ しょうかい
主な説を紹介しています。
つき きゅうれき つき な まえ ゆ らい い み おも せつ
月 旧暦の月の名前 由来・意味とされる主な説
しんねん むか しんるい あつ なかむつ つき い み
がつ むつき ・新年を迎えて親類などが集まり , 仲睦まじくする月という意味。
l 月 睦月 ねん はじ つき い み もと つき へん か
・1 年の初めの月という意味の「元つ月」が変化した。
さむ のこ きぬ ふく さら き き さら ぎ
・寒さがまだ残っていて , 衣(服)を更に着る「衣更着」。
がつ きさらぎ あたた よう き さら く き さら く い み
2月 如月 ・暖かくなり , 陽気が更に来る「気更に来る」という意味。
くさ き め は だ つき くさ き はりづき へん か
・草木の芽が張り出す月「草木張月」が変化した。
くさ き お しげ つき き くさ い や お い づき みじか
がつ やよい ・草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月」が短くなって ,
3月 弥生 い
「やよひ」となった。
う はな さ つき う はなつき みじか
がつ うづき
・卯の花(ウツギ)が咲く月「卯の花月」が短くなった。
4月 卯月 たね う つき う
づき
・イネの種を植える月「植月」。
た う つき さ なえづき みじか
がつ さつき
・田植えをする月「早苗月」が短くなった。
5月 皐月
た みず い つき みず つき
がつ み な づき
・田に水を入れる月「水の月」。
6月 水無月 な い み
(みなつき) (「無」は無いことではなく ,「∼の」を意味している。)
たんざく しい か か たなばた ぎょう じ ふみひらきづき へん か
がつ ふみづき
・短冊に詩歌を書く七夕の行事にちなんだ「文披月」が変化した。
7月 文月 いね ほ みの つき ほ ふみづき みじか
(ふづき) ・稲の穂が実る月「穂含月」が短くなった。
き ぎ は お つき は お つき みじか
がつ は づき
・木々の葉が落ちる月「葉落ち月」が短くなった。
8月 葉月 いね ほ は ほ は づき かり はじ く はつ き づき
(はつき) ・稲の穂が張る「穂張り月」。・雁が初めて来る「初来月」。
よる なが つき よ ながづき みじか
がつ ながつき
・夜が長くなる月「夜長月」が短くなった。
9月 長月 いね か つき いねかりづき へん か
(ながづき) ・稲刈りをする月「稲刈月」が変化した。
かみ まつ つき かみ つき かみなり つき かみなしづき
がつ かんなづき
・神を祭る月「神の月」
。雷のない月「雷無月」。
l 0月 神無月 い ず も たいしゃ ぜんこく かみ あつ かく ち かみがみ る す つき
・出雲大社に全国の神が集まり , 各地の神々が留守になる月。
しも ふ つき
がつ しもつき
・霜の降る月。
l l月 霜月
し そう ぶつ じ いそが はし まわ しわす
がつ しわす
・師(僧)が仏事で忙しく走り回る「師走」。
l 2月 師走 とし お とし は し き お しはつ
・年が終わる「年果つ」。四季が終わる「四極」。
わ ふうげつめい げんざい し よう きゅうれき げんざい こよみ か げつおそ げんざい き せつかん すこ
※和風月名は現在でも使用されることがありますが、旧暦は現在の暦より 1 ∼ 2 ヶ月遅いため、現在の季節感とは少しずれが
あります。
© この学習プリントは、ちびむすドリル 検索 で無料ダウンロードできます。
You might also like
- The Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessFrom EverandThe Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessRating: 4 out of 5 stars4/5 (396)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirFrom EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2146)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20066)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (41)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5681)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessFrom EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (812)
- It Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapFrom EverandIt Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (191)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 5 out of 5 stars5/5 (3302)
- Your Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyFrom EverandYour Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (103)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.From EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Rating: 4 out of 5 stars4/5 (345)